私がこんなにも背中を凝視しているのに蛍くんはまったく気付かない。飽きっぽく早々に投げ出してしまう私を根気強く机の前に座らせることを同じく早々に放棄した蛍くんは、私のことなんてすっかり忘れて数学の問題を解いている。暇を持て余して彼のベッドでごろごろ転がりながらも彼の背中を視界に入れれば、彼がシャーペンを走らせるたびに、背中の肩甲骨が微かに動くのがシャツ越しでも分かる。少し前まで学ランやセーターが彼の背中を覆っていたから、その白いシャツがやけに無防備に見えて、透ける体温になんだかどうしようもなくなってきた。いくらテストが近いからってこんなときまで彼女を放っておいて勉強に勤しむなんてナンセンスだよ蛍くん。だって春はこんなにも私の心をざわつかせる。
「 ねぇ蛍くん、触ってもいい?」
「………はぁ?」
私の突拍子の無い問いかけにそこでようやく蛍くんは振り返って私を見た。その顔には眉間の皺が刻まれていたけど、私はそれに気付かないフリをして答えを待たずに蛍くんとの距離を縮めて、その背中にシャツの上からそっと触れる。
「勉強の邪魔にしないようにするから」
「……ちょっと、僕まだ何も言ってないんだけど」
呆れてるような咎めるような声を漏らしながらも、私の申し出を汲んでくれたのか一応シャーペンの動きを再開させながら蛍くんが言う。その無防備な広い背中に手を這わせば、まだ真新しいけど少しずつ柔らかくなっていくシャツの感触と、その向こうにある骨張った彼の背中の温度が指先に伝わってくる。掌の中で蛍くんの肩甲骨が動くのがなんだかちょっと面白くて、そのまま撫でるようにあちこち触っていたら、蛍くんが勉強していた手を止めて、はぁ、と小さく溜息を漏らして首だけをこちらに向けて私を見た。
「 、気が散るんだけど」
「ねぇ蛍くん、女のひとって怒ると肩甲骨が動くんだって、こないだ読んだ小説に書いてあった。小鳥が羽ばたくみたいにここがぴんと立つんだって。男のひともそうなのかな」
「…君ほんと他人の話聞かないね」
「試してみてもいい?」
「 ? どういう、」
問おうとした蛍くんの言葉を最後まで聞かずに、体勢はそのままに後ろから蛍くんの腰に腕を回してぎゅっと抱きついた。縮んだ距離に便乗して、目の前にあった蛍くんの短い襟足が沿ううなじにわざと音を立てて唇を押し当てると、「 っ、」と蛍くんが小さく息を吸う音が聞こえる。ついでに舌も這わせてみようかと口を開きかけたところで、ぐるりと身体ごとこちらを向いた蛍くんに手首を掴まれ、そのまま後ろに押し倒された。「ちょっと、どういうつもり」手首を掴んだまま上から覆い被さるような体勢で、いつもより少し低めの苛立ったような蛍くんの声が私を射抜いて、思わず口角が上がる。
「何笑ってんの」
「 蛍くん、勉強はいいの?」
「 ……誰かさんのせいで気が散ったからね」
そう言って蛍くんはまるで最初からそうするつもりだったかのようにその背中を丸め距離を縮めてキスをした。そのままぺろりと唇を舐めて、続いて何度か重なるそれに私が溺れそうになっていれば、いつの間にか浮いた私の背中に腕を回した蛍くんがふと何かを思い出したかのように動きを止めた。
「それで、どうだったの肩甲骨は」
「よく分からなかった」
「なにそれ」
「でもいいんだ」
だから続きしてよ、と蛍くんの耳元で誘うように囁けば、蛍くんはわざとハァ、と大きく溜息をついて、ほんと君って厄介、と呆れ混じりの柔らかい声で言った。覆い被さる蛍くんの背中に腕を回せば、指先で蛍くんの肩甲骨が動いて、また自然に頬が弛む。蛍くんだってきっと子供っぽくて無邪気で悪戯っぽい要素でてきている。その背中に何が詰まっているかは、これからじっくり確かめてみることにしましょうか。
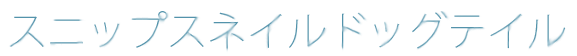
(140330 リクエスト企画より雰囲気おまかせな月島蛍)