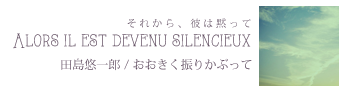「ノリが軽すぎて冗談だと思われてるんじゃねーの」
「エーー!冗談なんかじゃねェのに」
頭に両手を当てて思いきり仰け反れば、そういうとこだよそういうとこ、って泉が呆れたように頬杖をつきながら言った。「っていうかさ」机を挟んで向かい合わせに会話している俺のことを泉が正面から見据えて少しだけまじめなカオをする。「拒絶されたら、とか、考えないのかよ」そう言って俺を見る泉に、俺は首を捻る。うーん。でも、俺がスキなんだから、それでよくね? 「ふーん…」俺と一緒に泉も少しだけ考え込む。「でも、好きだからこそ言えないっての、あるだろ」その泉の言葉に、俺はますます首を捻る。うーん、なんとなく分かるような、全然分からないような。ムズカシイことは苦手だ。
「田島の場合、告白とかそういうかんじじゃねーもんなぁ」
「コクハクって、よくわかんね」
「それは俺に聞かれても。……あぁほら、ちょうどあんなふうに」
泉が指で示した場所に視線を移せば、この教室の窓際からちょうど眼下に見える校舎裏で男女二人が少し神妙な雰囲気で何やらやり取りを繰り広げている。告白か、あの様子じゃ男の方からかな。こんな人目につくとこでよくやるねぇ、と何度目かの溜息をつく泉の横で、俺は彼らから目を離せないままでいた。だって、あれは、あの後ろ姿は。「 …ん? ってか、あれ、じゃねぇ?」そう言って驚く泉の言葉を聞くや否や気がつけば足が走り出していた。オイ、田島! 背後から聞こえた泉の呼びかけは、もう俺には届いていなかった。
「なぁ、アイツと付き合うの」
我ながら不躾な質問だと思ったけれど、案の定は息を切らしながら駆けつけて開口一番そんなことを尋ねた俺のことを、じろり、と一瞥した。俺が到着した頃にはあの名も知らぬ男子は既にどこかに立ち去っていて、が一人立ち尽くしたままだった。は突然現れた俺に驚くでもなく、ただ静かな目をしていて、それが余計に俺の心をざわつかせる。
「……私のこと好きなんだってさ」
「っ そンなの、 俺だって、」
すきだ。それは今更になって急に現実味を帯びない言葉に思えて、口に出そうとしたのに喉の奥につっかえて出てこなかった。好きだ、だけど、何かが違う。違うのか?違わない。答えは分からない宙ぶらりんのまま頭の中がぐらぐらする。スキとかスキじゃないとかそんなよりももっとどろどろとした感情が鎖骨の下あたりで渦巻いてるのが分かる。悔しかったり苛立っていたり、そういった負の感情とも、また違う。もっともっと凶暴で、俺自身でも手に負えない何かだ。好きだからこそ、言えないっての、あるだろ。そう言った泉の声が脳裏に過る。なぁ泉、やっぱ、ぜんぜんわっかんないよ。
何も言わず黙ったままでいる俺を見て、がほんの少しだけ寂しそうな表情をする。そして口を結んで俺の横を足早に通り過ぎていこうとするのを、俺はの手首を掴んで制止した。が驚いたように目を丸くして俺のほうを振り返る。手首を掴んだのは最早反射だったけど、触れてしまったらもうだめだと、触れたからこそ痛いほどに分かった。だけどそんなの、もう遅い。
「俺、やっぱ、が欲しい」
このどろどろとした感情を、恋、と名前を付けることには躊躇う。だけど触れた華奢な手首の温度に、感触に、びりびりと体内がざわついて、このままどこかに連れ去ってしまいたいと思うこの妙な衝動がすべてだと思った。目と目が合ったまま、俺とのあいだに沈黙が横たわる。俺はもうに好きだとは口にしない。そしても、もう俺に、うそつき、とは言わなかった。